甲虫1(鞘翅目:しょうしもく/コウチュウ目) K1-3 クワガタムシ |
||||
| K1-3: | コクワガタ | スジクワガタ | ヒラタクワガタ | ミヤマクワガタ | ノコギリクワガタ | アカアシクワガタ | クワガタムシ♀ |
| チビクワガタ |
甲虫1(鞘翅目:しょうしもく/コウチュウ目) K1-3 クワガタムシ |
||||
| K1-3: | コクワガタ | スジクワガタ | ヒラタクワガタ | ミヤマクワガタ | ノコギリクワガタ | アカアシクワガタ | クワガタムシ♀ |
| チビクワガタ |
| #K001−1〜3 コクワガタ♂(クワガタムシ科)[拡大][拡大] | #K001−4〜5 コクワガタ♂(クワガタムシ科) |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 撮影C:2005/05/22 浜田市国分町 石見海浜公園 | 撮影C:2006/07/11 温泉津町福光 |
| 全長♂16.5〜45mm、♀20〜28mm。全体はツヤ消しの黒色で、胸部の横への張り出しが丸く見えますからコクワガタです。♀や若い♂の胸部背や頭部には光沢が見られます。上翅に列にならない点刻が密に見られます。成虫はクヌギ,ナラなどに集まり、樹液を舐めます。幼虫はそれらの木の枯れた部分や腐った部分を食べます。 ■大アゴのノコギリ歯:コクワガタは普通片側に大アゴ内側からに突き出た大歯1個と先端に返し歯を1個もっています。これらの歯は写真の様に目立たないものや、ないものもいるそうです。 2006.02.11オオアゴが成長する記述削除 |
■コクワガタは卵から1〜2年かけて成虫になります。夏に蛹になり、秋頃成虫に羽化し、その後越冬状態に入ります。翌年の6月頃目覚め、夏活発に行動し、交尾して♀はクヌギの朽木に卵を産み付けます。 ■全長:図鑑に書いてあるクワガタムシの大きさは、大アゴを入れた全体の長さで、全長で表記されています。その他の甲虫に長いキバ(大アゴ)をもったものがいますが、クワガタ以外は体長で表記されていることがほとんどです。またセミやバッタの大きさを表すとき、翅の端まで含めた全体の長さを表す全長をよく使います。セミやバッタを全長で表すと、腹部を想像することなく見た目で分かりやすい特徴があります。 |
| #K067 スジクワガタ♂(クワガタムシ科) | |
 |
 |
| 撮影C:2004/08/19 温泉津町福光 民家k裏山 | |
| 全長♂17〜35mm。上翅のスジは見えませんが大あごの形が成長したスジクワガタです。♀のスジは消えることがありませんが、♂は大きくなると消えてしまいます。幼虫は広葉樹など朽ちた木を食べます。成虫はクヌギのどに集まり、樹液をなめます。 |
| #K026 ヒラタクワガタ♂(クワガタムシ科) | #K026−1 ヒラタクワガタ♂(クワガタムシ科) |
 |
 |
| 撮影C:2006/07/01 温泉津町福光 民家k裏山 | 撮影C:2006/07/01 温泉津町福光 民家k裏山 |
| 全長♂26〜78mm,♀22〜40mm。幼虫はブナ,クヌギなどの腐りかけた木を食べます。成虫はブナ,クヌギ,ヤナギの樹液に集まります。 全長♂26〜78mm,♀22〜40mm。名前の通り平たく、大腮(たいさい/おおあご)内側の大歯から先端まで、細かい鋸歯状(きょしじょう)です。幼虫はブナ,クヌギなどの腐った植物質を食べます。成虫はブナ,クヌギ,ヤナギの樹液に集まります。 ■大腮(たいさい):大アゴとも呼ばれるあごから突き出した2本の牙に見える部分。腮(あご,えら・サイ)人の顔に見られるえら骨(大辞林) ■鋸歯状(きょしじょう):鋸(のこぎり)の歯のようにギザギザした状態 |
■日本のヒラタクワガタはインドシナ半島が原産で、今から500万年前に南西諸島から日本に入って来たそうです。よって東南アジアのヒラタクワガタと日本のヒラタクワガタは同じ名前でも遺伝的には500万年の差があるそうです。しかし最近東南アジアからペットで輸入された種類が、飼い主の不注意で野に放たれ、交雑種が多くなっているそうです。 |
| #K026−2 ヒラタクワガタ(クワガタムシ科) | |
 |
 |
| 撮影S10:2012/10/09 温泉津町 |
| #K133,−1 ミヤマクワガタ♂(クワガタムシ科)[拡大] | #K133−2,−3 ミヤマクワガタ♂(クワガタムシ科) [拡大] |
 |
 |
 |
 |
| 撮影C:2005/08/01 温泉津町福光 民家k裏山 | 撮影C:2005/08/01 温泉津町福光 民家k裏山 |
| 全長(大アゴ含む)♂43〜72mm,♀32〜39mm。体色は赤褐色から黒褐色で、胸部から前側の頭部,大アゴには光沢がありません。胸部と頭部背には黄褐色の短い毛がまばら生えていてサビた感じに見えます。大きさには大中小と数種いて、小型のものは大アゴが小さく別種の様な形をしています。大型の♂の頭部の縁は反り返り、耳に似た出っ張りがあって、似たノコギリクワガタと区別できます。写真は大型種の若い成虫です。幼虫はブナ科の枯れ木を食べ、2〜3年かけて成虫になります。成虫はブナ科の樹木やヤナギの樹液を舐(な)めます。 | ■ミヤマクワガタの♂の特徴として肢が長い特徴があります。特に脛節(けいせつ)が長く、他のクワガタに比べ肢全体が長く見えます。 ■写真の様に、♂の大アゴ付け根,頭部,胸部背には黄褐色の毛が沢山生えたものがいます。若い成虫に見られ、やがて抜け落ちて行きます。 |
| #K133−4,−5 ミヤマクワガタ♂(クワガタムシ科) | #K133−7,−8 ミヤマクワガタ♂(クワガタムシ科)[拡大] |
 |
 |
 |
 |
| 撮影C:2006/07/01 温泉津町福光 | 撮影C:2006/07/23 18:43 温泉津町福光 |
| #K133−15 ミヤマクワガタ♂(クワガタムシ科) | #K133−16 ミヤマクワガタ♂(クワガタムシ科) |
 |
 |
| 撮影C:2006/08/03 温泉津町福光 | 撮影C:2006/08/03 温泉津町福光 |
| #K141,−1 ノコギリクワガタ♂小型種(クワガタムシ科) | #K141−6,−7 ノコギリクワガタ♂小型種(クワガタムシ科) |
 |
 |
 |
 |
| 撮影C:2005/09/05 温泉津町福光 民家k裏山 | 撮影C:2006/07/11 温泉津町福光 |
| 全長(大アゴ含む)♂36〜71mm、♀24〜30mm。体は闇赤褐色から黒褐色で、♂の上翅は赤味が強いです。成虫はクヌギやナラ,カシ,ニレ,ヤナギなどの樹木に集まり樹液をなめます。幼虫はクヌギなどの朽木(くちき)を食べます。 卵は夏から秋にかけて朽木に産み付けられ、1〜3ヶ月で孵化します(1齢幼虫)。この年は幼虫で越冬し、腐植物質を食べて成長し1回,2回と脱皮して3齢幼虫となります。良く成長すると夏頃蛹(さなぎ)になりますが、成長できないと後1年かけて蛹になります。蛹は秋頃羽化し、この年は成虫で越冬し、翌年の夏頃朽木から這い出てきます。 |
■小型種:写真の様に大きさが小さい♂は大アゴの形が違います。大型のものはへの字に曲がり牛の角の様に見えますが、小型のものは小さく真っ直ぐで、和ばさみの様に見えます。小型種には大アゴの内側に細かいギザがあり、鋸歯状(きょしじょう)です。大型種の方は小突起(内歯)が前側に6〜8対ありますがでこぼこで、名前ほどノコギリ歯に見えません。 |
| #K141−2,−3 ノコギリクワガタ♂大型種(クワガタムシ科) | #K141−4,−5 ノコギリクワガタ♂大型種(クワガタムシ科) |
 |
 |
 |
 |
| 撮影C:2006/07/10 6:44 温泉津町福光 | 撮影C:2006/07/11 温泉津町福光 |
| #K165,−2 アカアシクワガタ♂(クワガタムシ科) | #K165−1,−3 アカアシクワガタ♂(クワガタムシ科) |
 |
 |
 |
 |
| 撮影C:2006/08/13 温泉津町井田 | 撮影C:2006/08/13 温泉津町井田 |
| 全長♂24〜45mm。全体は黒褐色で光沢があり、後胸板と腿節(たいせつ)が赤褐色をしています。この特徴的色から名前が付けられています。♂の大腮(たいさい)の先には2〜3本の小歯が見られます。成虫はブナ,コナラ,ヤナギの樹液に集まります。幼虫はそれらの朽木を食べます。 | ■腿節(たいせつ):足の腿(もも)にあたる太い部分 |
| #K215 チビクワガタ(クワガタムシ科) | #K215−1 チビクワガタ(クワガタムシ科) |
 |
 |
| 撮影EOS:2008/04/30 益田市匹見町 | 撮影EOS:2008/04/30 益田市匹見町 |
| 体長11〜15.5mm。体は光沢のある黒色です。マメクワガタムシによく似ていますが、眼縁突起が前に向かって広がっています。大腮(たいさい)は短く、先が少し上を向いています。朽木に生息し、成虫は一年中見られます。 | チビクワガタの胸部背の点刻は、弱いようです。 |
| 名前 | コクワガタ | オオクワガタ | ヒラタクワガタ | ミヤマクワガタ | ノコギリクワガタ | スジクワガタ |
| 外見 | 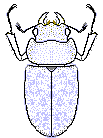 |
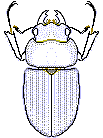 |
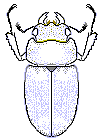 |
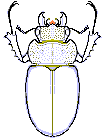 |
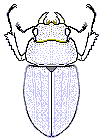 |
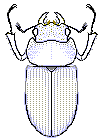 |
| 全長 | 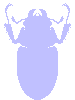 20〜30mm |
 36〜42mm |
25〜34mm | 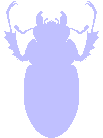 32〜39mm |
24〜30mm |  14〜20mm |
| 上翅の点刻 | 点刻が密に見られるが縦に点刻列をつくらない | 縦に溝のようなスジ、条溝がみられる | 縦に点刻列がみられる | |||
| 前肢の脛節 | 真っ直ぐ | 真っ直ぐ | 内側に湾曲 | 内側に湾曲 | ||
| 光沢 | ||||||
| その他の特徴 | 特に大きい | 前肢脛節の形とトゲが特徴的 | 特に小さい | |||
| 過去にクワガタの繁殖をされていた永田さんのご意見 | 1.真上から見たシルエットは凹凸のない楕円形 2.上翅表面は均等にざらつきがある 3.色や大きさは図鑑の記述にあてはまらない |
| #K026−3 ヒラタクワガタ♀(クワガタムシ科) | #K026−4 ヒラタクワガタ♀(クワガタムシ科) |
 |
 |
| 撮影C:2004/08/19 温泉津町福光 民家k裏山 | 撮影C:2006/07/11 温泉津町福光 |
| 全長♀25〜34mm。2008.08.30永田氏同定 | ★2008.08.30名前訂正、永田氏ヒラタクワガタ♀と同定 |
| #K141−9 ノコギリクワガタ♀(クワガタムシ科) | #K001 コクワガタ♀(クワガタムシ科) |
 |
 |
| 撮影C:2006/08/03 温泉津町福光 | 撮影F:2003/07/30 温泉津町福光 くぬぎ林 |
| 全長♀24〜30mm。2008.08.30永田氏同定 ■過去にクワガタを繁殖されていた永田さんのご意見 1.真上から見たシルエットは凹凸のない楕円形で、触角のないゴキブリの様な姿をしている。 2.上翅表面は均等にざらつきがある。 3.色や大きさは図鑑の記述に当てはまらない。今まで見たものは、色が漆黒から明るい赤茶色、朱色といってもよいぐらいの色まで。腹部の色,模様も単色からアカアシクワガタそっくりな色模様まで様々。 サイズは22〜43mm。 |
全長♀20〜28mm、クヌギ,ナラなどの樹液をなめます。 ★このクワガタは本ホームペジ開設時に、一番最初に載せた記念の写真です。ぼけていても削除できません。 |
| #K001−1 コクワガタ♀(クワガタムシ科) | #K001−2 コクワガタ♀(クワガタムシ科) |
 |
 |
| 撮影:2010/08/22 六甲山逆瀬川上流 | 撮影:2010/08/22 六甲山逆瀬川上流 |
| ※2010.08..22永田さんに問い合わせ ◆2010.08.26 17:10回答メール: 上翅の点刻では、コクワガタかヒメオオクワ(場所的に)の可能性を考えましたが、前胸背板の形でコクワガタの雌で間違いないと思います。茶色っぽいのは、土か朽ち木が擦って付いたものと思います。 |
ヒラタクワガタの場合、前足がやや湾曲しているのと、艶があり滑らかな上翅に条状の点刻があります。画像の個体のように、ざらついたようにも見える細かい点刻と、不明瞭な条状の点刻はコクワかヒメオオです。ノコギリは体型が違い、全体にざらつきがあります。どの種類も、色や大きさは当てになりません。 |
| #K133−6 ミヤマクワガタ♀(クワガタムシ科) | #K133−10 ミヤマクワガタ♀(クワガタムシ科) |
 |
 |
| 撮影C:2006/07/23 18:43 温泉津町福光 | 撮影C:2006/08/03 温泉津町福光 |
| 全長(大アゴ含む)♀32〜39mm。 | |
| #K133−11,−12 ミヤマクワガタ♀(クワガタムシ科) | #K133−13,−14 ミヤマクワガタ♀(クワガタムシ科) |
 |
 |
 |
 |
| 撮影C:2006/08/03 温泉津町福光 | 撮影C:2006/08/03 温泉津町福光 |
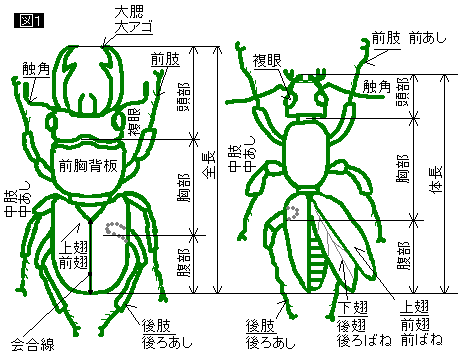 |
甲虫目(約37万種)> ・クワガタムシ ・コガネムシ,カナブン,ハナムグリ,カブトムシ ・ハンミョウ,オサムシ,マイマイカブリ,ヒラタムシ,ゴミムシ ・ゲンゴロウ,ミズスマシ,ガムシ ・シデムシ,エンマムシ,ハネカクシ,アリヅカムシ,キノコムシ, カツオブシムシ,シバンムシ,シンクイ,ヒョウホンムシ ・ホタル ・タマムシ,ジョウカイ,コメツキ,ヒラタムシ,キノコムシ,キスイ ・カミキリムシ ・ゴミムシダマシ,クチキムシ,アカハネムシ,ハムシ,ハナノミ ・テントウムシ,カミキリモドキ,ツチハンミョウ ・ゾウムシ,オトシブミ,キクイムシ 甲虫目は上翅を含め全体に硬い皮膚に覆われています。後翅は薄く柔らかで折りたたまれた状態で上翅の内に収まっていますが、飛ぶ時はこの後翅を羽ばたいて飛びます。その時上翅はバランスをとる役目しかありません。ほとんどの甲虫は、完全変態の形態をとります。 |
| 大あご/大腮(たいさい):腮(あご) 前ばね/上翅(じょうし)/前翅(ぜんし)/翅鞘(ししょう):鞘(さや) 後ろばね/後翅(こうし) 前あし/前肢(ぜんし)/前脚(ぜんきゃく) 中あし/中肢(ちゅうし)/中脚(ちゅうきゃく) 後ろあし/後肢(こうし)/後脚(こうきゃく) 前胸背板(ぜんきょうはいばん),会合線(かいごうせん) |
| [注]撮影:又は撮影F:FUJIFILM FinePix−F410, 撮影C:OLYMPUS C−750UZoom, 撮影D:KONIKA MINOLTA DiMAGE−Z3 |
Copyright ©2003-2011 Fukutomi design office All rights reserved